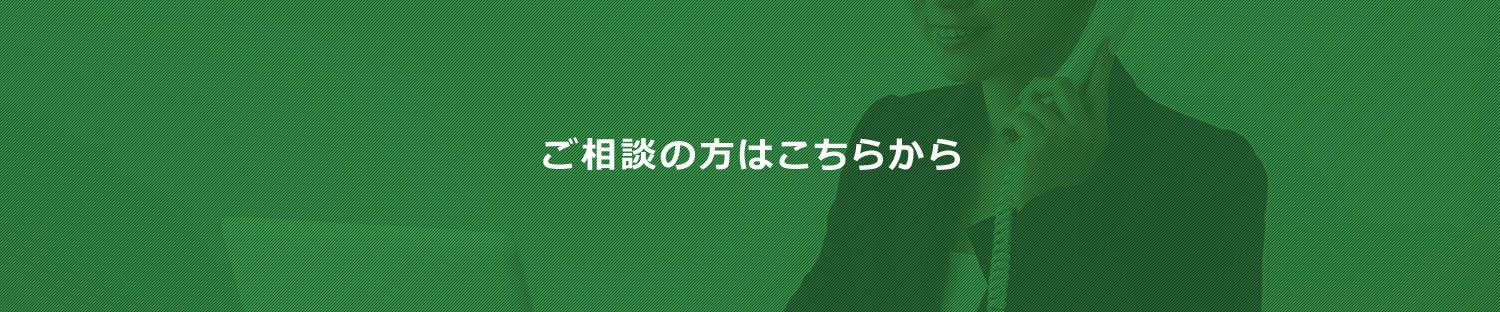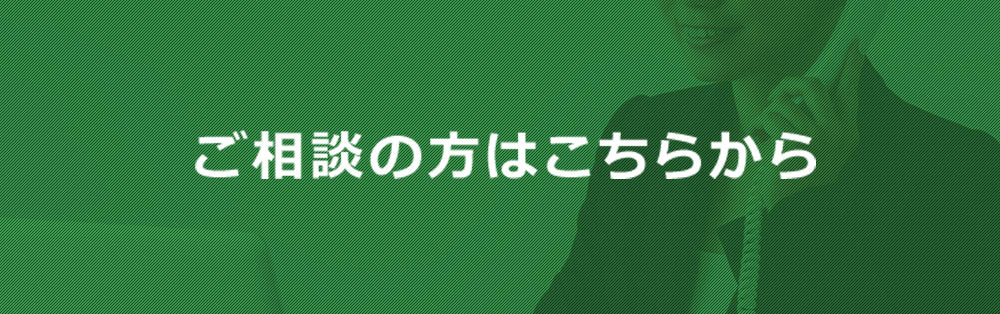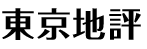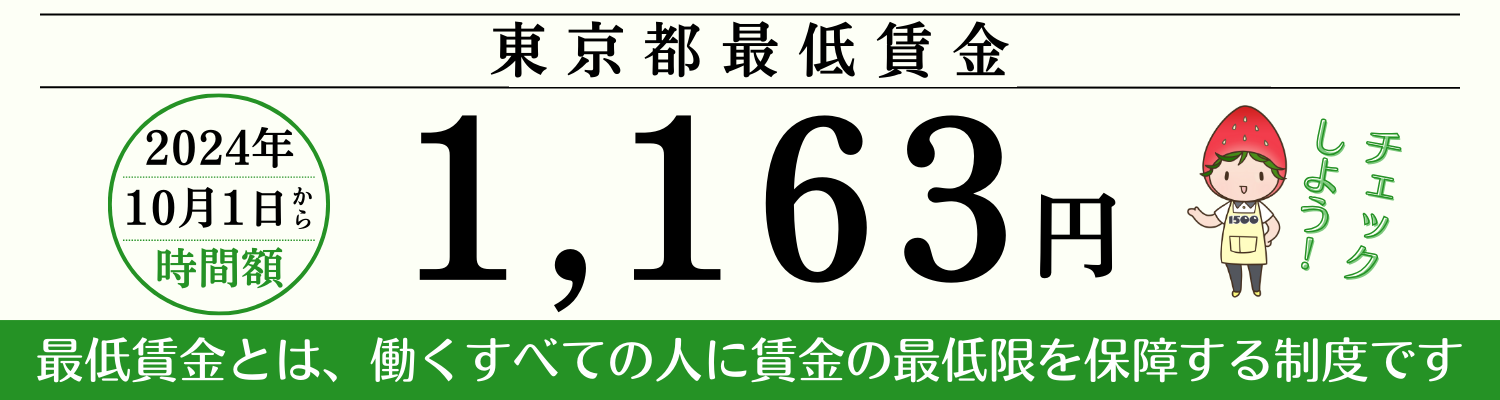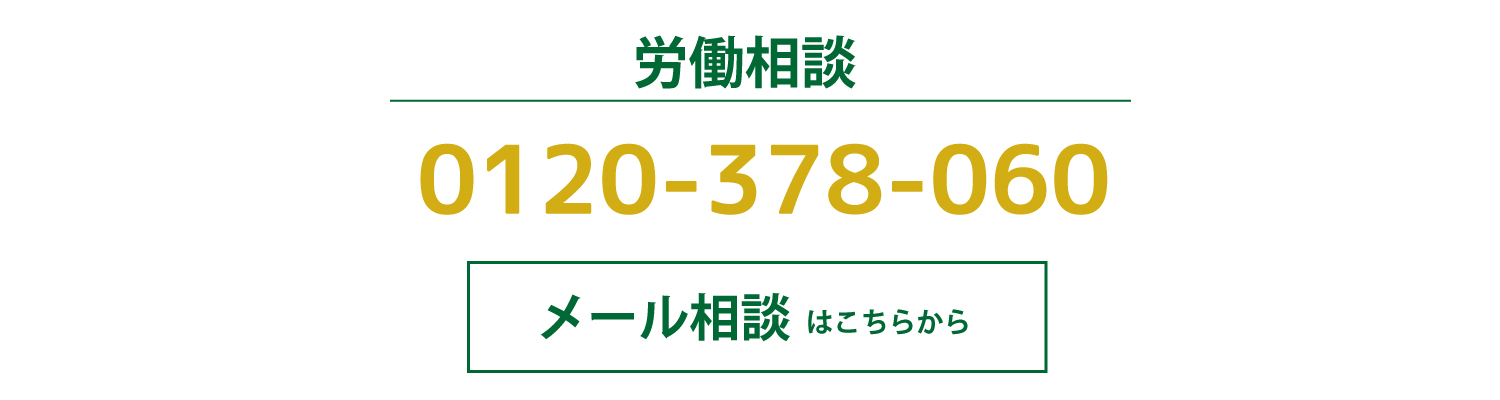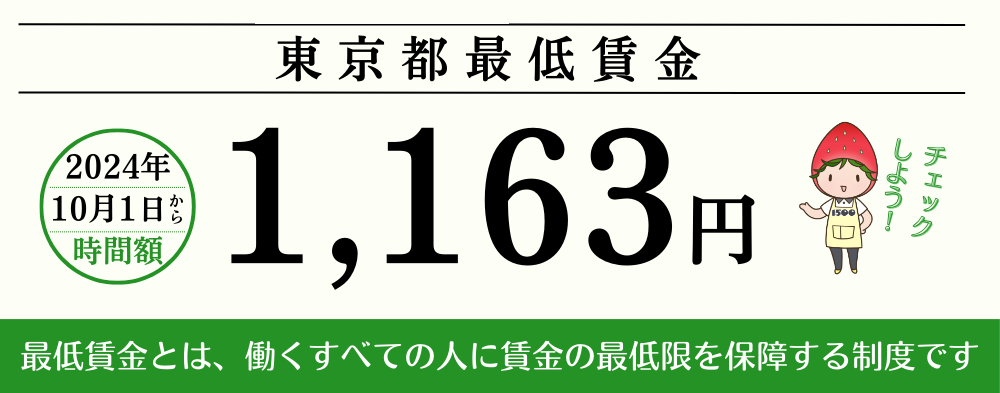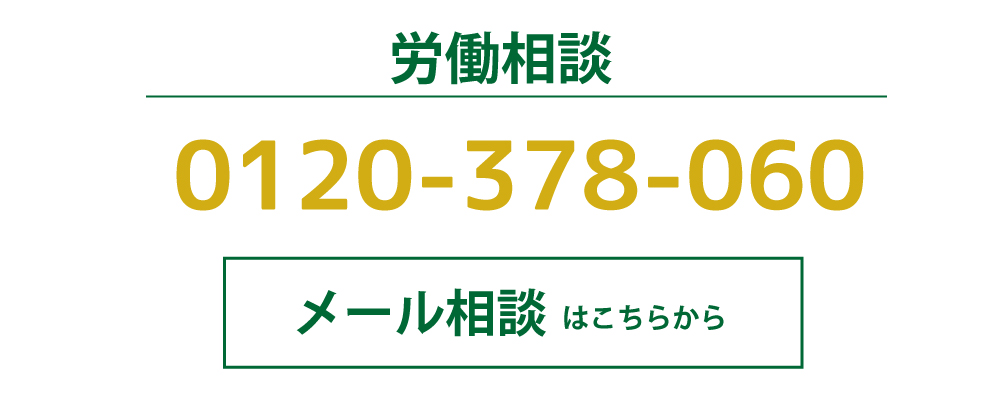国民運動
2025.07.04
消費税は減税、インボイスは廃止を! 国会学習会・財務省要請実施

女性・ジェンダー平等
2025.07.04
はたらく女性スクエアや労働相談の状況 東京都と労働情勢について懇談

調査・研究
2025.06.23
東京で”ふつう”に暮らすには時給「2000円」必要 【最低生計費試算調査2025年版】

事務局長談話
2025.06.16
【25都議選 事務局長談話】東京で暮らすすべての人に投票を呼びかけます。

国民運動
2025.06.12
「心に杭は打たれない」の意味を捉え直そう 砂川闘争70周年のつどい
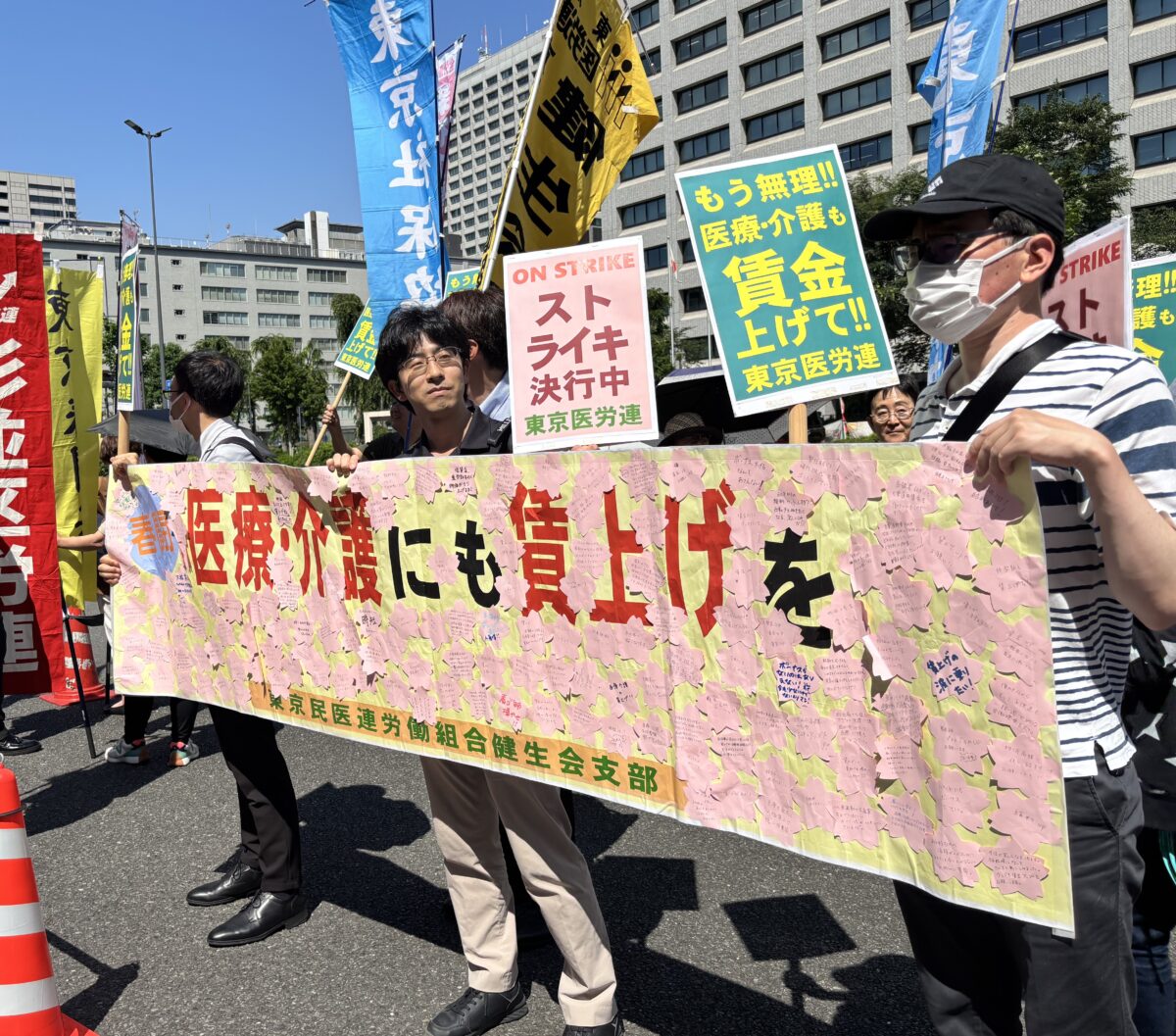
賃金・労働
2025.06.11
~財務省は国民の命を守れ~ ケア労働者の賃上げと診療報酬の改定を
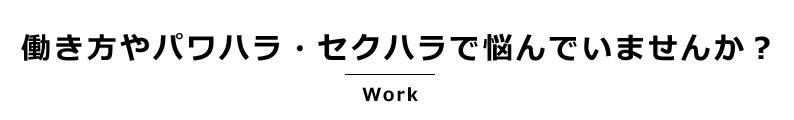
働くことで悩んでいませんか?その悩み、労働組合で解決できるかもしれません。
ひとりで悩まず、東京地評にご相談ください。
ひとりで悩まず、東京地評にご相談ください。
労働相談ホットライン
0120-378-060
労働相談はこちら